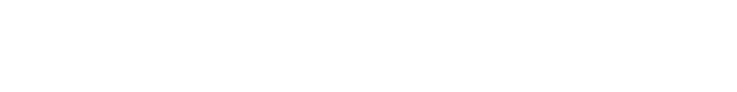医学生・研修医の方へ
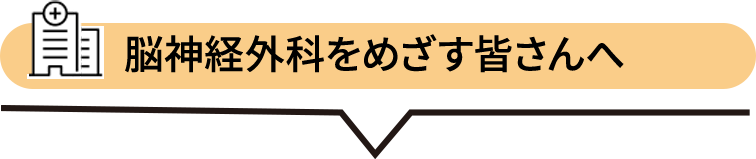
京都大学脳神経外科学教室の特長は、京大に脈々と伝わるリベラリズムと、本邦で屈指といえるマンパワーです。東は静岡から西は高知・小倉まで30施設を超える地域中核的な公的ないし準公的病院を中心に合計約50の関連病院としてもち、教室同門の脳神経外科医は約450名です。大きなマンパワーというスケールメリットを生かすことにより様々な選択が可能であり、画一的ではなく個々の教室員の人生観に合わせた多様なキャリアプランニングが可能になります。所帯が大きいからこそ、選択肢が多くなるということです。最近は毎年のように産休に入る女子医師が続いていますが、休暇中の知識維持のためのセミナーや育休明けのサポートなども年々充実してきています。国内他大学や海外からの研修・留学者も多く、知己がひとつの病院や大学教室だけにとどまらず、人の輪がひろがります。また、同じ釜の飯を食う同級生の数も多く、同世代との切磋琢磨の中から生涯の友人を得ることができます。


脳神経外科が対象とする領域は、脳血管障害、脳腫瘍、脳機能、疾患、脊椎、脊髄疾患、小児疾患、外傷など、さまざまな専門領域があります。京都大大学脳神経外科で学んだ医師が各専門領域各研究領域をリードする立場で活動しています。
また、個人の希望に沿った専門領域を学び、最先端の研究をすることができます。海外学会での発表海外施設の診療体験海外施設のカンファレンスなど、国際的な活躍をすることもできます。
京大病院が得意としている治療は、巨大脳動脈瘤や脳動静脈奇形あるいは巨大な脳腫瘍など他施設では治療が困難な疾患、機能的脳外科の手法を用いて大脳高次機能を温存しながら手術するグリオーマ治療やてんかん外科、治療症例数では本邦でも屈指といえるもやもや病などの特異な疾患などです。また、本邦で最大級のスペースを誇るstroke care unitがあり、急性期脳卒中も多く搬入されています。さらに、本邦で初めて導入された3テスラ術中MRIや企業と共同開発した世界初といえるポータブルCTなど手術室における機器整備も最先端の陣容となっています。 ハード面だけではなく、画像診断の読影や病態解釈など大学ならではの知識面でのきめ細かい指導とさまざまな最先端の研究にふれることができるのも京大の魅力のひとつです。

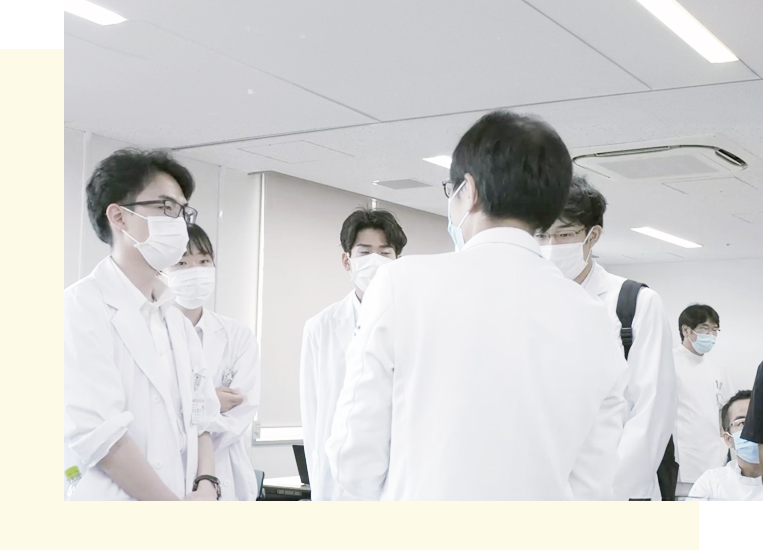
京大病院で後期研修を開始する場合には、京大病院でこのような研修を1年~1年半行った後に、地域中核的な病院に赴任して術者としてのトレーニングを受けます。専攻医が実際の術者として経験できる機会は、いわゆるhigh volume hospitalとして有名な施設よりも、地方都市において地域中核的な施設のほうが多く提供できます。ここでもそのような関連病院を数多く持つという京都大学脳神経外科学教室のスケールメリットを有効利用することができます。
脊椎脊髄・先天奇形などの小児脳神経外科・てんかんなどの機能的脳神経外科については、high volume hospitalといえどもなかなか専門的に研修することができないのが現実です。京都大学の研修プログラムでは上記の地域中核的な病院における研修の後にこども病院において小児先天性疾患を、脊椎脊髄疾患を専門的施設において研修する専門領域ローテート研修を行います。なお、機能的脳神経外科については京都大学や北野病院が得意とする分野です。そして、この専門領域ローテート研修の後に、国立循環器病研究センター・北野病院・神戸市立医療センター中央市民病院・倉敷中央病院・小倉記念病院などの大規模病院に赴任して専門医取得を目指してもらうことになります。
平成16年に始まった臨床研修制度の影響で、一時的には大学院を志望する若者が激減しましたが、最近は専門医を取得した後に大学院で研究する若者が多くなりました。京都大学脳神経外科学教室では現在30名を超える大学院生が臨床的および基礎的な研究に従事しています。京都大学脳神経外科学教室の大学院生はいわゆる社会人大学院生ではなく、非常勤勤務以外には基本的には研究専従です。また、決して大学院に入ることが義務化されているわけではなく、大学院に入らず関連病院で臨床を続ける若者もいます。これらも各教室員の自由な選択に委ねられています。
 2025年度 教室説明会
2025年度 教室説明会
- 第1回教室説明会
2025年4月20日(日) 手術体験9:00~
医局説明会 12:00~
懇親会 13:00~ - 第2回教室説明会
2025年7月21日(月・祝) 手術体験9:00~
医局説明会 12:00~
懇親会 13:00~ - 第3回教室説明会
2025年9月21日(日) 手術体験9:00~
医局説明会 12:00~
懇親会 13:00~
開催場所はそれぞれ、京都大学医学部です。
参加ご希望の方は、登録フォームより参加申し込みをお願いいたします。
 2025年度 脳神経外科手術体験ビギナーセミナー
2025年度 脳神経外科手術体験ビギナーセミナー
- 第1回脳神経外科手術体験ビギナーセミナー
2025年 4月20日(日) 9:00~13:00 - 第2回脳神経外科手術体験ビギナーセミナー
2025年 7月21日(月・祝) 9:00~13:00 - 第3回脳神経外科手術体験ビギナーセミナー
2025年9月23日(日) 9:00~13:00
参加ご希望の方は、登録フォームより参加申し込みをお願いいたします。